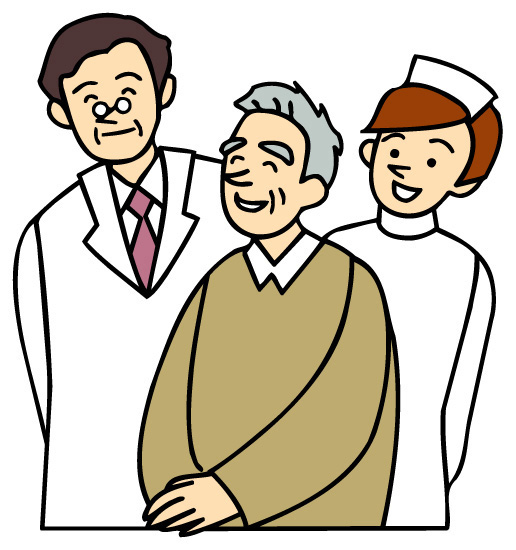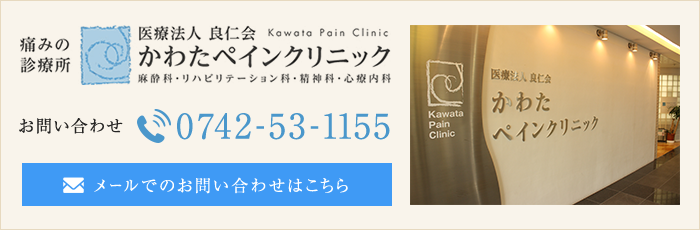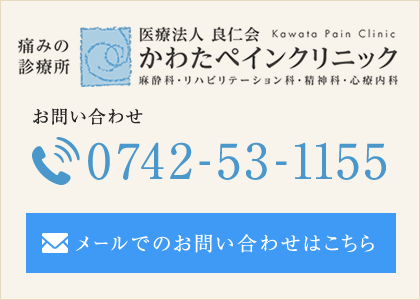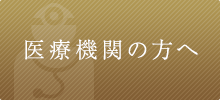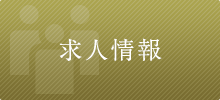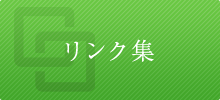痛みは、傷や心が絡み合って、脳が感じています。
「痛み」は、単純な反射的感覚ではなく、心の動きや情動を伴った苦しみ・不安など人が「感じる」体験だと考えられています(国際疼痛研究学会)。
痛みの原因は大きく次の4つに分けられます。
①傷から末梢神経を通じて脳へ伝えられる痛み
(膝をすりむいたり、熱いヤカンに触れた時の痛み等、外傷)
②末梢神経そのものの痛み
(帯状疱疹後神経痛・糖尿病によるシビレや痛み等、外傷はないが神経そのものが原因で起きる痛み)
③心因性の痛み
(神経・体にはあまり問題ないのに痛い、心理的問題・社会的要因等多くの要素で成り立つ痛み)
④脳や脊髄の痛み
(交通事故等で、脳や脊髄が損傷して感じる痛み)
上述のそれぞれの痛みと治療薬について、お話ししていきたいと思います。
今回は、「①傷から末梢神経を通じて脳に伝えられる痛みと治療薬」についてお話しします。
一般的な痛みで多くの方がイメージする痛みのほとんどがこの痛みで、「痛い」と感じている傷の場所で炎症が起き、痛みセンサーを興奮させる反応が生じて起こる痛みです。
この痛みの治療の代表薬が、普段、皆様が病院や薬局で処方される痛み止めで、大半が非ステロイド鎮痛薬(NSAIDs)で、ロキソニン・セレコックス・ボルタレン等です。
これらの薬は、①の痛みで起きる"炎症や痛みセンサーを興奮させる反応"を抑えてくれます。
言い換えると、NSAIDsが効くという事は①の痛みの可能性が高く、その薬が合っている痛みと言う事ができます。
他方、これらの薬では痛みが少ししか改善しない、又は、全く効果のない場合、感じている痛みは後述の②~④の痛み、又は、①~④の痛みが組み合わさっている状態と考えられ、この状態でNSAIDsを飲み続けるといたずらに服薬量が増えたり、効果はないけれども副作用の可能性が高くなることもあります。